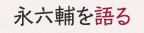
掲載日:2017/07/07

旅番組「遠くへ行きたい」は、昭和45年(1970)10月から始まった。そこから半年間、つまり26週の旅人役を引き受けたのが永六輔さんだった。放送作家として、あるいはラジオの旅番組「永六輔の誰かとどこかで」のパーソナリティとして、多忙を極めていた永さんが、一週ごとに、3泊4日の撮影スケジュールにつきあうと決めたのだ。時には3日どころか2日の日程しか取れない場合も許されるとしても、並大抵の覚悟ではない。テレビの旅番組に賭けようとする思いがあったのだろう。
その第1回のディレクターを務めたのが私だった。何人かのディレクターが交代で担当したが、前から面識のあるディレクターは誰もいなかった。それでも見事に永さんは26回の旅人の役割を演じた。そこから見えた永さんの話をしようと思う。
自己を律する人
第1回の目的地は岩手県だった。永さんと国鉄上野駅の改札口で待ち合わせることにした。私たちは、上野駅を撮影する予定だったので出発時刻よりかなり早く着いた。永さんが改札を背に床に腰をおろして仮睡していた。その様子から私は、永さんは別用で地方に出かけていて、夜行で上野駅に戻り、待っていたのだ、と推測した。永さんは、岩手でのロケの間、早朝から上野駅にいた理由を一言も喋らなかった。
別の旅の時、永さんが夕食を終えてから自室で原稿を書いて徹夜したらしいことが解ったこともあった。ロケの間に原稿の締切日があったのだろう。永さんは、私たちに徹夜のことを一言も言わなかった。
察するに永さんは自分の苛酷なスケジュールをスタッフが知ってしまうと、スタッフに精神的な負担を感じさせてしまう。自分が引きうけた以上、愚痴は言わずきちんと仕事をこなそうと決意していたのだと思う。自分を律することに厳しい人だったのだ。
そう考えると、永さんが作詞を止めた理由にも思いが及ぶ。「遠くへ行きたい」が始まった頃、永さんは作詞を止めていた。その理由を永さんはこう説明していた。「冗談でまわりの人に作詞を止めようと思うと言ってみたら誰も反対してくれなかった」。だから止めざるをえなくなった、これが永さんの説明である。
永さんは、1959年の「黒い花びら」を始めとして「上を向いて歩こう」「遠くへ行きたい」「こんにちは赤ちゃん」など、大ヒット作を連発していた。その作詞活動を止めたのだ。これも「察するに」だが、膨大な著作権料が入ってくることが、日頃の自分の生き方と相容れなくなったからではないのか。
地方に出かけて身を粉にして働いて何がしかの労賃を得て暮らしている常民の話を聞く、というのが、民俗学者・宮本常一から教わった永さんの生き方だったはずなのだ。流行歌の作詞家の生活はそれを裏切るものだ、と永さんは考えたのかもしれない。身を律したのだ。
大衆芸能の継承者
放送批評家の松尾羊一さんは、永さんをこう評価している。「明治の近代化以降は専らインテリの『書く文化』中心だったがそこに、終始『見る、聞く、語る』という行動文化を貫いたのが永六輔だ」(毎日新聞2016・7・21夕刊)
話芸家としての永六輔、である。私はそれに加えて「見せる」芸の人としての永さんを評価したい。「遠くへ行きたい」で、そこに見えるものを即興で描写したり、そこらあたりの石や小枝を拾い集めて、今いる所を地図にして示したり、「美しい風景には、私ではなく、美しいモデルさんを」と注文したり――毎回、場面ごとに「見せる工夫」を最大限にやったのが永さんだった。永さんは、テレビの特性をよく知っていた。話芸とともに「視覚化する」ことの大切さを知っていた。江戸時代からの大衆芸能を引き継いだのがテレビである。永さんはテレビ時代の大衆芸能者であった。
新しいドキュメンタリーへの挑戦
旅番組「遠くへ行きたい」は、国鉄の「ディスカバリージャパン」キャンペーンの一環として生まれた。このキャンペーンの生みの親は、広告代理店・電通の藤岡和賀夫さんだった。「遠くへ行きたい」の第1回の試写会の様子を藤岡さんは、著書「華麗なる出発」の中でこう書いている。
「『遠くへ行きたい』の第一回で、永さんが啄木記念館で書翰を読むシーンがある。暗い館内。照明が朗読の終わるとともに消えて闇になる。永サンの気配だけが残る。読み終った一瞬の永サンのふと力を抜いた部分に、不思議に旅人の心情が浮ぶ。演出者はその暗い闇のシーンまで放送に使っている。
ところが、試写が終わったとき『NGカットがあった』と専門家がいい出す。しかし素人はその部分を面白いと素直に認める。その危ないバランスで作品は作られてゆく。」
実は、永さんは、そのシーンを入れこんだ編集を初めて見た時、素直に受けいれた。私の意図をすぐに理解したのだろう。
永さんは、その後、スタッフをコント風に画面に出すようになった。録音のKさんは、いつも永さんに「爺や、爺や」と呼びかけられては画面に登場していた。ふたたび藤岡さんの言葉を引く。
「『遠くへ行きたい』では、意識的にカメラの撮影者や演出者の注文する声が、画面の中へ平気で登場して来る。虚構と現実が交錯する。新しい現実がそこには生起してくる」
ひとり旅を大勢のスタッフで撮っている、という「事実」を、永さんと私たちは「娯楽」として提示したのだ。何の気負いもなく。
「テレビ・ドキュメンタリー」への出演は永さんにとって初めてのことだったろう。ドラマ出身の私も初めての経験だった。私たちは「素人」だった。それが前例に捕らわれない新しいドキュメンタリーを生んでいったのだと思う。
(注1)
『遠くへ行きたい』(とおくへいきたい)は、読売テレビを制作局として日本テレビ系列で放送されている紀行番組。 1970年(昭和45年)10月4日放送開始以降、現在の放送を続ける最長寿番組である。
(注2)
華麗なる出発―ディスカバー・ジャパン (1972年) (毎日選書) 藤岡 和賀夫 (著)
出版社: 毎日新聞社 (1972) ASIN: B000J9RZTG 発売日: 1972
 今野 勉(こんの つとむ)
今野 勉(こんの つとむ)
演出家・脚本家。1936年秋田県生まれ。東北大学文学部卒業。東京放送(TBS)入社、テレビ演出部配属。ドラマ「土曜と月曜の間」でイタリア賞(ドラマ部門最高賞)。シリーズドラマ「七人の刑事」ギャラクシー賞大賞。1970年番組制作会社「テレビマンユニオン」創立に参加。
旅番組「遠くへ行きたい」、3時間ドラマ「海は甦える」など、ドキュメンタリーやドラマで新しい世界を開拓。1995年「こころの王国~童謡詩人金子みすゞの世界」で芸術選奨文部大臣賞受賞。長野冬季オリンピック開閉会式プロデューサー(会場演出)、武蔵野美術大学映像学科教授を務めた。著書に「テレビの青春」、「宮沢賢治の真実」(新潮社)など。現在、(株)テレビマンユニオン取締役最高顧問、放送人の会会長。

※ 今野勉さんの執筆した生原稿をPDFでご覧いただけます。[PDF:3.5MB]